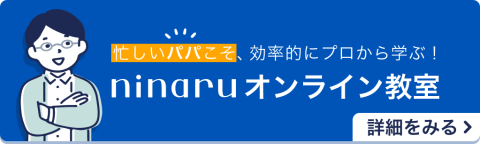出産後はママ・パパともに少しゆっくりしたいところですが、さっそく赤ちゃんに関する手続きをする必要があります。産後に慌てたり忘れたりしないよう、事前に手続きの種類や期日を把握し、パパが動ける体制を整えておきましょう。
この記事では、赤ちゃんが誕生したら必要になる手続きを紹介します。準備や申請に役立ててくださいね。
赤ちゃんが生まれたら必要な手続き
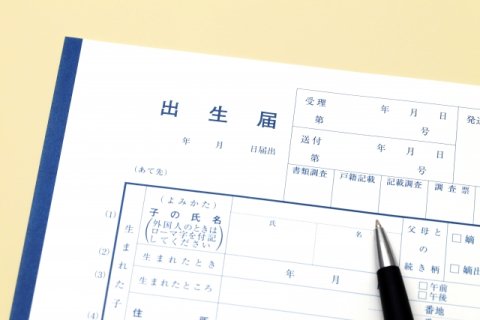
① 出生届の提出
出生届は赤ちゃんを戸籍に登録する書類。一般的に、出産した産院で出生証明書とセットで渡されます。
マイナンバーカードの申請書も一緒になっていることが多いので、合わせて申請するのがおすすめです。
※国外出産は3ヶ月以内
● 提出先:本籍地や出生地、住民票のある市区役所か町村役場のいずれか
● 提出者:両親、代理人でも可能
提出の際、出生届のほかに申請者の本人確認書類と母子手帳が必要です。忘れ物がないよう、自治体のホームページ等も確認しておきましょう。
※自治体によってはオンライン提出が可能な場合もあります
② 児童手当の申請
児童手当は、子どもが0歳から高校修了まで(18歳になって迎える最初の年度末まで)受け取れる給付金。2か月分ずつ偶数月に支給(年6回)されます。
支給額は子ども1人あたり、下記になります。
● 3歳未満:15,000円
● 3歳以上〜小学校修了前:10,000円
● 中学生〜高校生:10,000円
※第3子以降は0歳〜高校卒業まで30,000円
● 提出先:住民票がある市区役所や町村役場
● 申請者:養育者のなかで所得が高い方
原則として申請した月の翌月分から支給されます。遅れた月分の手当は受け取れないので、早めに申請しましょう。
③ 健康保険の加入
赤ちゃんの健康保険の加入も手続きが必要になります。パパ・ママが加入している健康保険の種類によって、期限や提出先が変わるので事前に確認しておきましょう。
※企業の健康保険や共済組合の場合は勤務先に要確認
● 提出先:勤務先の窓口(健康保険・共済組合)、住民票のある市区役所や町村役場(国民健康保険)
● 申請者:両親のどちらか(扶養に入れる側)
④ 乳幼児医療費助成の申請
乳幼児医療費助成は、赤ちゃんが病気やケガで病院を受診したときに、年齢にあわせて医療費の一部もしくは全額を助成してもらえる制度。
赤ちゃんの健康保険証が発行されたらすぐに申請が必要なため、手続きに必要な申請者の本人確認書類や健康保険証は、あらかじめ準備しておくといいですよ。
● 提出先:住民票のある市区町村役所
● 申請者:両親のどちらか
※自治体によってはオンライン提出が可能な場合もあります
リスト化して、スマートに手続きを!
産後の手続きは複数あり、実際のところ面倒に感じる人も少なくありません。必要な手続きをチェックリスト化して把握できるようにしておくと便利ですよ。
また、今回の記事ではみなさんに共通する手続きをご紹介しています。分娩方法や状況によっては、他にも産後に必要な手続きが生じることもあるので、以下もあらかじめ知っておくと安心です。
□ 医療費控除
□ 未熟児養育医療給付金
□ 自治体・企業からのお祝い金
手続きをスマートにこなし頼れるパパになるためにも、ninaruが実施している「赤ちゃんの手続き」講座でより詳しく学んでみませんか?
▼参加者の声

手続きが多くあることを知れました。手当が貰える月などもはじめて知り、自分がしっかり動かないといけないことが分かりました。

資料をまとめたシートがもらえてありがたかったです!
40分間と短い時間のなかで、産後にやるべき手続きについてギュッと凝縮してご紹介しています。無料なので、ぜひ気軽に参加してみてくださいね!
※この講座は隔月で開催しています。次回の開催案内を受け取りたい方は下のボタンからご登録ください。
また、これ以外にもパパ向けの講座をたくさんラインナップ。下のバナーをタップしてチェックしてくださいね!